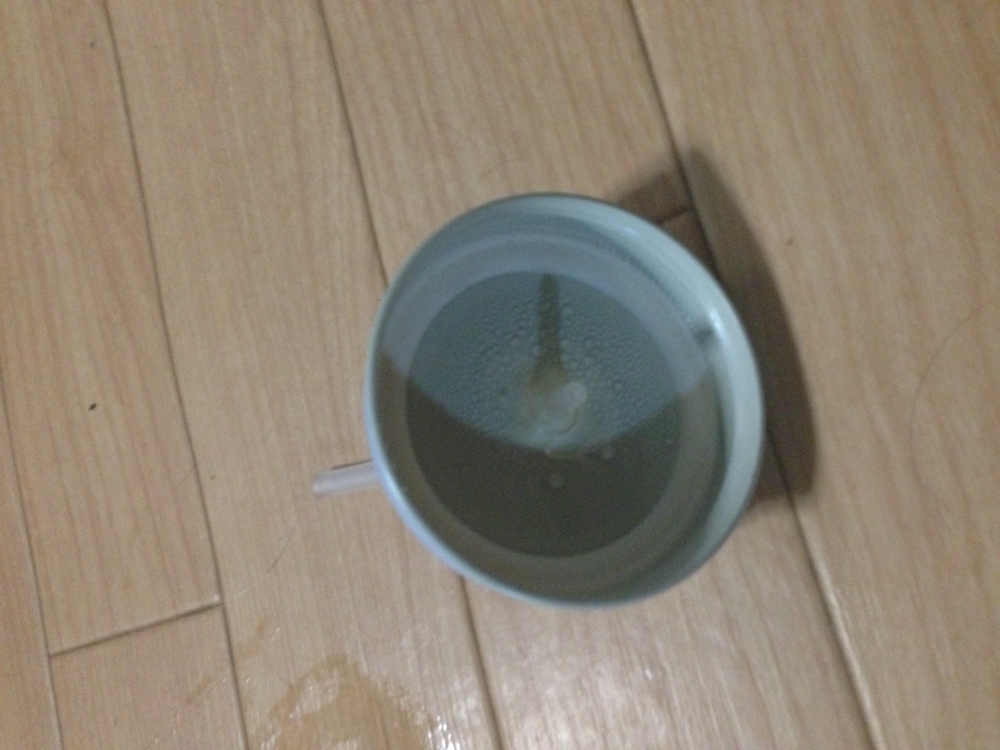ブログ
2013.05.22
アクアリウムといったらCO2でしょ!
水槽に水草が増えてくると、水に含まれているCO2の量が不十分で、植物の発育不良の元です。
そこで、アクアリウム愛好家達は、高額なCO2添加装置なるものを設置して二酸化炭素を補っているわけですが、この装置安いものでも数万円とお高く、ボンビーな管理人には手が出ません。
そこで、「貧乏は創造の母」なのです。
Google先生にお手伝いしてもらいながらも、自作いたしましたので、ご紹介いたします。
 まずは、完成品を。実はこれタケノコなんかを保存しておくビンなんです。
まずは、完成品を。実はこれタケノコなんかを保存しておくビンなんです。
① 蓋にエアホースのジョイントサイズ(6mm)の穴を開けます。(ジョイントがキツいくらいがちょうどいいかも...)
② その接合部分にエポキシボンドなんかで接着します。そして、さらに気密性を高めるためにシリコンコーキングで上塗り!
③ 完成品は荷造用のポチポチでくるんでいます。これは、後で紹介するイースト菌発酵を持続させるために保温材としての役割を果たしてくれます。
[中身のレシピ]
① 200mlの水に砂糖100gを沸かした水に溶かします。
② さらに、火を止めた状態で、ゼラチン(粉末)を6gまぜて、よくかき混ぜます。
③ 粗熱をさまして、先ほどのビンに投入!
④ 後は、冷蔵庫に入れて固まるのを待ちましょう(大体2時間くらいで固まるはずです。)
⑤ 固まったら、そのビンに45℃~50℃位のお湯を300ml入れます。
⑥ ここでイースト菌の登場!管理人は最初5gで試しましたが、8g位入れてもOKです。
(入れすぎると発酵が進み、ゼラチン床がすぐに無くなってしまいます)
(この時、砂糖を10g位混ぜると発酵が早く始まります)
なんちゃって「バブルカウンター」設置
中身は、こんな感じです。
イースト菌の発酵が進むと、中の水が白濁し泡立ってきます。
1週間~10日ほど経つと、イースト菌が糖分を分解しアルコールが生成されて甘酒の様な匂いがしてきます。
しかし、このアルコール分でイースト菌の活性が弱まってきますので、上澄み(アルコール分)を捨て、捨てた量と同等の水分を補充したら、少しイースト菌を足しておきます。
下に固まっている砂糖ゼラチンは、2週間~20日位持ちますが、無くなったら最初の手順で、また作ります。
管理人宅では、白砂糖が少なかったので、ザラメを使用しました。ゼラチン床が茶褐色なのは、そのせいです。
CO2添加装置の動画でも、お気付きかと思いますが、ビンからエアストーンまでのチューブには、バブルカウンター(自作)と逆流弁が挟まれており、その先に三股コックが付いています。これで、CO2の供給ON・OFFをコントロールしています。
非常にシンプル且つ低コストですが、CO2の供給量調整は微妙で在宅中は、こまめにチェックが必要です。
なぜかというと、水槽内の魚の個体数が少なければ問題ないんですが、ある程度の個体数だと酸欠状態になりかねません。
動きの活発なウグイなんかが多いと、ドジョウがちょくちょく水面に上がってくるようになりました。
多分、酸素不足なのだと思います。
では、失敗作のご紹介。
これは、100円ショップで購入した、密閉(?)タッパです。
パッキン部分の気密性が甘く、容器自体も軟弱なせいか、うまく供給出来ず失敗。
今は、ザリガニのマンションと化しています ^ ^ ;
コメント
- 魚を入れてみよう! ①
- main
- その後の水槽 ②